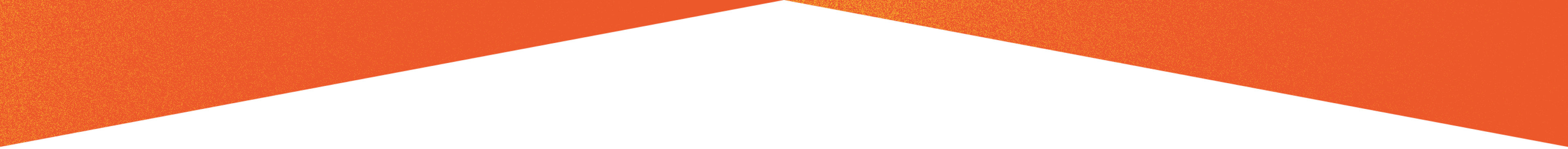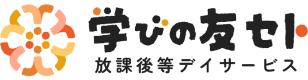3月12日瀬戸市放課後等デイサービス「学びの友セト」職員研修を実施
「授業UD学会」の会報誌が届きました。
武田は現在一会員ですが、学会の立ち上げにつながる「国語の授業UD研究会」の立ち上げメンバーでした。
学会現理事長氏とは20年来の付き合いです。
桂氏の前職筑波大学付属小学校教諭時代には尾張旭市に何度となく来ていただき、模範授業や講演をしていただき授業のについて指導をしていただきました。
桂聖氏は現在「共愛学園前橋国際大学准教授」です。
20年前に筑波大学付属小学校の研究会に参加後、
懇親会で「教師の仕事は、教科の授業論を戦わせることではなく、目の前の児童・生徒がいかに変容するのかという視点で授業を組み立てることが大切である」
と主張されてみえる桂氏の言葉に「桂氏に一生ついていこう」と決意したことが今の自分に繋がっていると思っています。
職員研修の内容「授業で特に必要なことは教師の価値観を押し付けないという事」
授業で特に必要なことは
「教師の価値観を押し付けない」
という事です。
言葉にすれば簡単ですが、
専門的な知識が豊富な教師ほど押し付けがちになってしまいがちです。
特に国語の授業で「登場人物の気持ちやその変化」を「どう思う」と聞きがちです。
しかし、それでは文学の面白さ楽しさは味わうことができない児童・生徒がほとんどです。
その上、「ここが面白い」とか「ここが凄い」と教師の価値観を押し付けて授業がおわりでは国語が好きになる児童・生徒は減るばかりですね。
「ごんぎつね」で何を学んだかが問われるはずなのに、
「ごんぎつね」を読んだことだけが問われるのが日本の国語授業であるとよく言われてきました。
「ごん」の気持ちの変化(いたずら心からつぐないの心)と「兵十」の反応、
そして結末の兵十の「ごんおまえだったのか」
新見南吉の著作で日本全国において使用されている教科書に掲載されている不朽の名作ですね。
思いの行き違いを読み取ることができたらOKですよ。
ある時「ごんぎつね」の授業後、
ある児童の
「ごんは死んじゃったの」
発言で思わぬ展開になりました。
意見が「死んだ」「死んでいない」の真二つに分かれたのです。
「先生はどう思うの」と聞かれ、
武田は
「死んだか死んでないのかは判りません」それよりも尊いのは
「授業後にこんな話し合いができたことだと思います」
と結んだのです。
職員研修を受けて
余談ではありますが、
その後「ごんぎつね」を何度も読み直す児童がたくさんいたことにびっくり。
「教師の仕事は、教科の授業論を戦わせることではなく、
目の前の児童・生徒がいかに変容するのかという視点で授業を組み立てることが大切である」
ということを実感できる幸せな時間を味わうことができました。