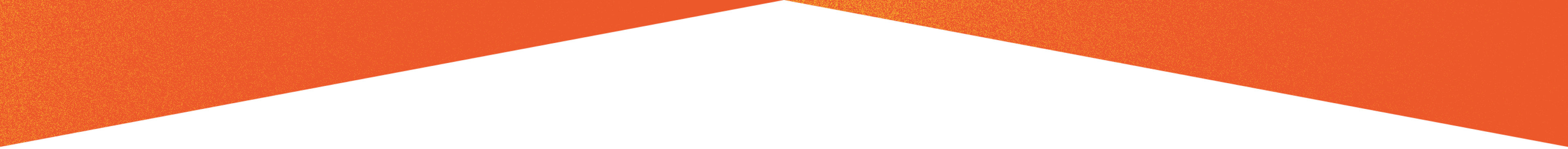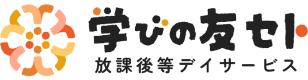指導方針のスタンダード⑤(地域学習って何ですか?)
「瀬戸で学んでよかった」とか
「尾張旭で学んでよかった」と
心から思って小・中学校を卒業していく児童・生徒がどのくらいいるでしょうか?
「あなたの学んだ地域にはどんなことがありますか?」
と聞かれた人々が
「何も無い」と答えるシーンがテレビやラジオでよく見聞きされます。
なぜ日本人は自分の住んでいる地域のことをうまく紹介したり自慢したりすることが不得意になってしまうのでしょうか?
以前〇〇中学校に勤務していた時、
英語の授業にAETとしてイギリス人女性講師が勤務していました。
彼女は日本の文化や伝統について関心があり、
英語の教師を介して、
私に日本の文化や伝統について質問してきました。
丁寧に応答していた時、
日本人の英語教師が次のような感想を述べました。
「自分は今まで英語が話せることが国際化になると信じて学習してきました。
しかし、イギリス人の彼女が日本のことをよく知っているだけでなく、
イギリスとの文化や伝統との違いを認識しながら、質問しているのを見て、
自分がいかに日本のことを学んでこなかったかということが良く分かった」と言いました。
その後半年の間2人と私は日英の文化について学びを深めました。
今でも忘れられない一言があります。
それはイギリス人の彼女が
「アヘン戦争から日本人が学んで、明治維新につながったのですね。
アヘン戦争を起こしたイギリスのことはどうしても好きにはなれないが、
アヘン戦争の事実を忘れてはいけないと肝に銘じます。」
まさしく「歴史に学ぶ」であり、
「稽古照今」ということを彼女は言っていたのだと思います。
歴史教育の最終目標は「知識の習得ではなく」
「過去から学ぶ姿勢」を身に着けることです。
そのためには自分の住んでいる地域の過去を知ることではないでしょうか?
そうすることで「瀬戸・尾張旭で学んでよかった」
胸を張り「瀬戸・尾張旭の自慢ができる」子どもたちを育成することも国際化につながるのです。
そんなカリキュラムをつくることも、学習のスタンダードの一つです。
そのカリキュラムにつて順次紹介していきます。